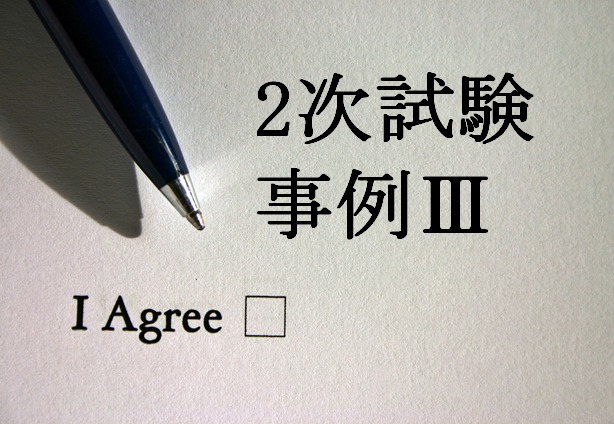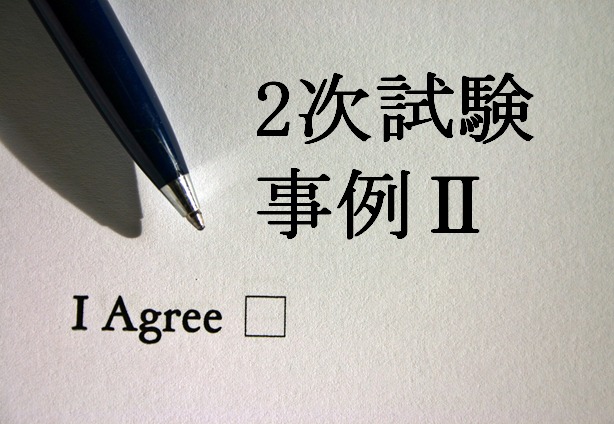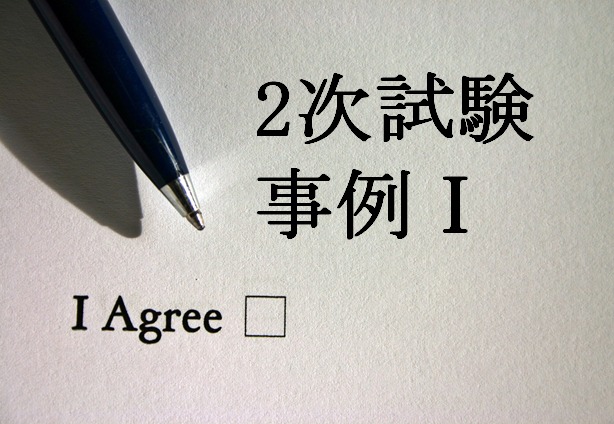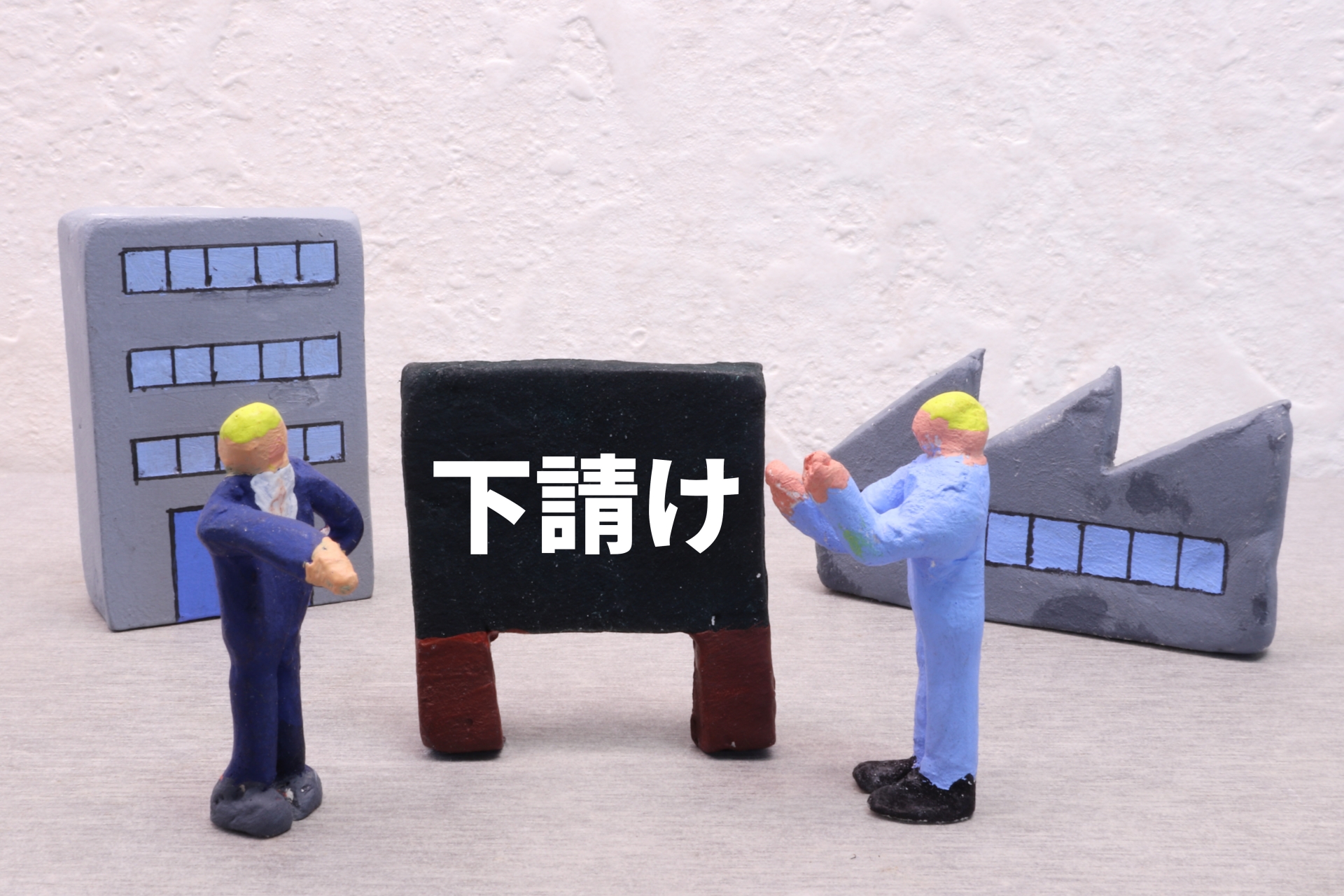「ふぞろいな合格答案」の活用方法
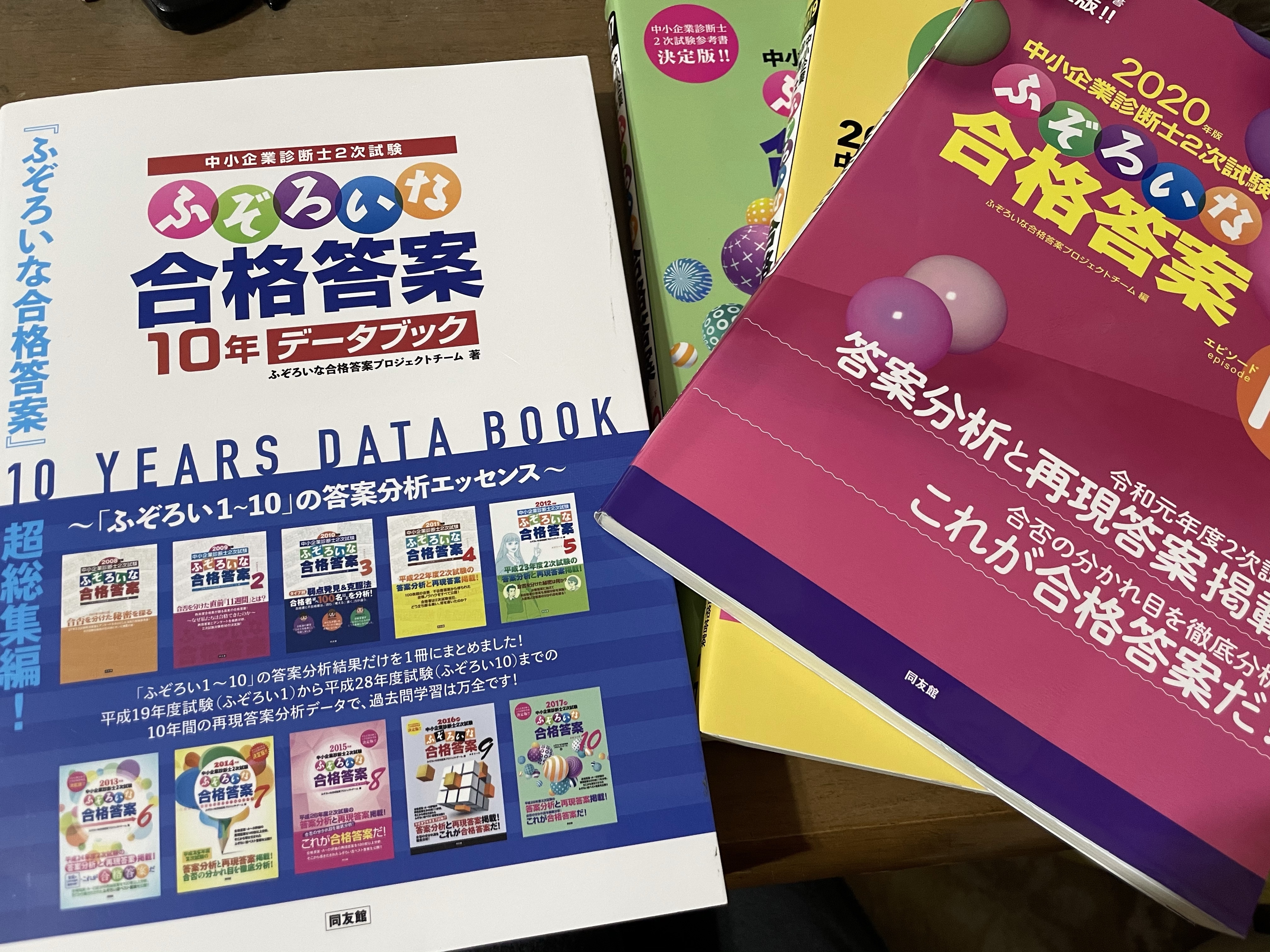
こんにちは。ぶらんちです。今日は2次試験対策の金字塔「ふぞろい合格答案」のご紹介です。
ふぞろいな合格答案とは
ふぞろいな合格答案とは、同友館が発行している2次試験対策用の参考書です。毎年本試験での実際の回答(再現答案)を募集し、集まった2~300名分の再現答案を分析して制作されています。
中小企業診断士試験2次試験の対策をするうえで何に困るでしょう。それはズバリ、2次試験の採点方法や模範解答が一切公表されていないことです。
本書は「実際に合格した答案には何が書かれていたのか」、「合格を勝ち取った人はどのような方法で合格答案を作成したのか」など、受験生の疑問や悩みを解決すべく、実際の合格答案を数多く分析することで、実態のつかみにくい2次試験の輪郭をリアルに追及しています。
また2次試験では80分間という時間のなかで設問文を読み、出題者の題意を汲み取ったうえで、事例企業における課題やその対応策を解答することが求められます。そのために必要な勉強方法や解法・テクニックなども合格者の中から提供しています。
ふぞろいな合格答案は主に以下2つの内容で構成されています。
- 再現答案を分析して作成した「ふろぞい的模範解答」
- 合格者たちのやり方をまとめた「2次試験の解法」
特に独学者にとっては2次試験対策の羅針盤となるものであり、具体的な解答作成プロセスを身につける上でほぼ必須のアイテムといえるでしょう。
最大の特徴はキーワード採点
ふぞろいの最大の特徴は、模範解答に採点基準が書いてあることです。
独学する上で特に困るのが、自分の作成した解答が合格に近づいているのかが分からないことですよね。各資格予備校の模範解答は内容がバラバラだし、そもそも80分で同じ内容が書ける気がしないものばかりです。
その点、ふぞろいは実際の受験生の答案を分析して作成しており、「このくらい書ければ合格圏内なんだな」という感覚が掴みやすいです。
その上で「このキーワードが含まれていれば5点」などと詳しく書いてあるので、自己採点することができ、合格に近づいていることを実感することもできます。
実際に、ぶらんちの再現答案を採点してみましょう。
令和元年度事例Ⅰ 第3問
A 社は、新規事業のアイデアを収集する目的で HP を立ち上げ、試験乾燥のサービスを展開することによって市場開拓に成功した。自社製品やサービスの宣伝効果などHP に期待する目的・機能とは異なる点に焦点を当てたと考えられる。その成功の背景にどのような要因があったか。100 字以内で答えよ。
HPを情報発信だけでなく情報収集ツールと捉え、双方向コミュニケーションに焦点を当てたこと。試験乾燥のサービスを通じ、自社の高い乾燥技術を情報発信するとともに、潜在顧客4のニーズの収集4を行った。
⇒8点/20点(ふぞろい採点基準)
上記は本試験当日に書いたものの再現答案です。何を問われているのか全く分からず、とにかくそれらしい言葉でマスを埋めた感じでした。当時はそれなりに形になったと満足していたのですが、ほとんどが全く点に繋がっていないことが分かります。
その後、いろいろと過去問分析など2次試験対策を行い、自分なりの型が出来てから再作成した答案がこちらです。
要因は、①試験乾燥サービスを通じ、様々な市場との接点ができたこと4、②潜在市場の見えない顧客4に用途を問う2ことでターゲット市場を明確化2できたこと、③高い営業力2で販売チャネルを構築2できたこと、である。
⇒16点/20点(ふぞろい採点基準)
前回よりも明らかに良くなりましたよね(自画自賛)。このように、「採点結果の上昇=解答作成プロセスの定着」と判断できるため、学習計画も立てやすくなりモチベーション向上にもつながります。
採点結果に振り回されるな!
ただ、このキーワード採点というのは、なかなかの曲者です。
ふぞろいだけで2次試験対策をしてしまうと、どうしても「キーワードを入れ込むこと」に注力しがちです。
受験生当時、勉強仲間と答案を見せ合って議論することもあったのですが、総花的な内容でキーワード盛り盛りだけど何が言いたい文章なのかよく分からないということも多々ありました(自分も含めて)。
- 潜在顧客のニーズを収集4し、営業力を発揮4して販売チャネルを構築2した。
⇒ HPで収集した情報を基に、積極的な営業活動で販路拡大したんだな - 販売チャネル2がない中、営業力を発揮4して潜在顧客のニーズ収集4を行った。
⇒ 営業が頑張ってニーズ収集??HPの話はどこに行った??
最近の本試験の傾向は「最大の理由は何か」など核心を問う問題が増えてきており、キーワードだけ詰め込んでも点数が伸びない可能性は大いにあります。
ふぞろいのキーワード採点に頼りすぎると、本来は論点が明確でわかりやすい答案が一番という本質を見失う危険性があるので注意です。

TACの全国模試もキーワード採点
ふぞろいから少し離れますが、TACの答練もキーワード採点です。まあ最大手で受講生が多く、公開模試も毎年2,000名超が受験するほどの人気のため、採点者のリソースを考えてもある程度は仕方がないとは思います。
ただ、最も利用者の多い「ふぞろい」や「TAC」のどちらもキーワード採点をされてしまうと、総花的に書いた方が点数が伸びやすいと受験生は誤解してしまいます(実際に伸びやすいかは分からない)。この状況が、答練では成績が良いが本試験に受からない受験生を生み出す要因になっているのではないか、と思っています。
注)あくまでぶらんちの私見です。どちらも毎年多くの合格者を輩出していることもまた事実ですので、誤解のなきよう…。
ぶらんち的ふぞろい活用術
解説を重点的に読む
ということで、ぶらんちは自己採点よりも課題抽出のためのツールとして主に使っていました。
特によく読んだのが、有名人の名前をもじったような名前の講師+受験生2名が、あれやこれやと議論を交わしながら、設問をどう解釈すればよかったのか、どこをポイントにして答案をまとめれば良かったのかを解説しているページです。
ぶらんちはこの解説を重点的に読み、「他の受験生に比べて自分に足りない部分はどこか」「次に活かすにはどうすれば良いか」を徹底的に分析してました。
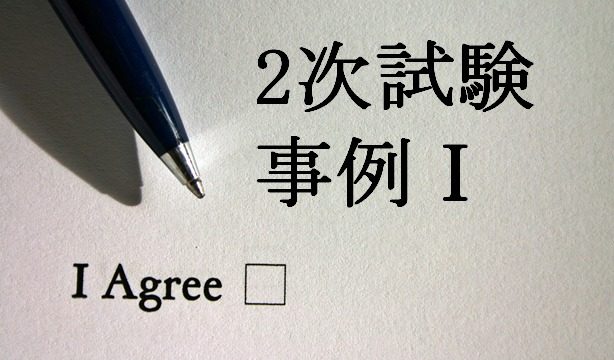
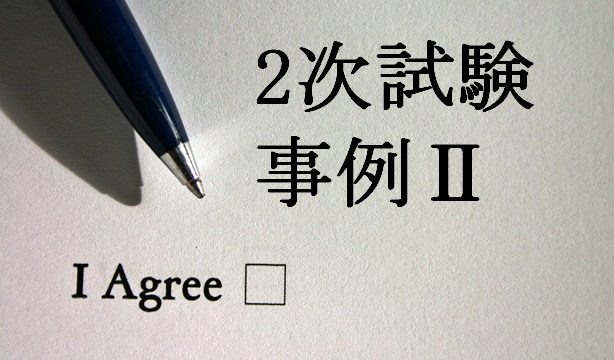
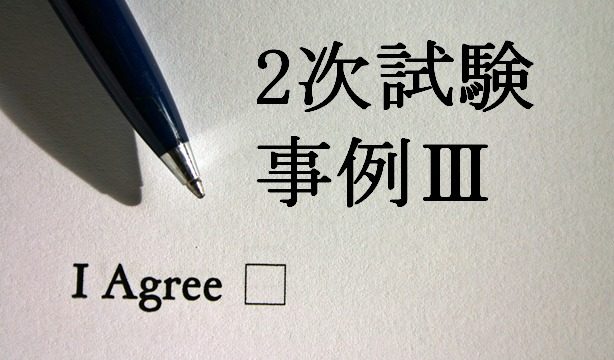
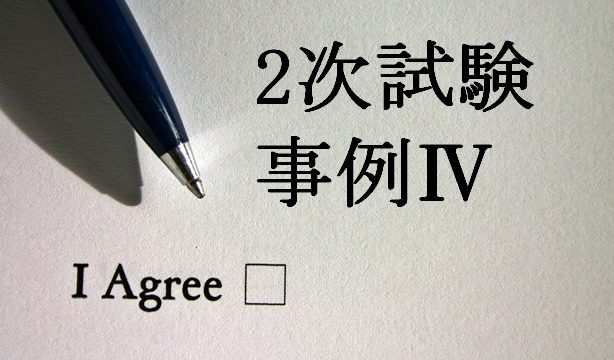
自分流のベスト答案を作る
ふぞろいの模範解答の中にも「キーワードを盛りすぎて何が言いたいかよく分からない文章」の時があります。このような場合は自分だったらどうまとめるかを考えます。
答案をまとめるのに十分なキーワードは揃っているので、どう編集すれば「論点が明確でわかりやすい答案になるか」を考えるわけです。
結局、正解のない茨の道を進むことになるわけですが、それが自分なりの解答プロセスを築き上げることになるのだと思います。
模試はLECも受けよう
先ほどTACの話をしましたが、当然LECも公開模試を実施しています。
規模はだいたいTACの10分の1くらいです(模試の結果からの推測)。ただ、その分LECの方が添削が丁寧で、答案に対するきめ細かいフィードバックを受けることができます。
もともとLECは「一貫性」「妥当性」を重要視しており、TACとは逆に総花的な答案は点数が伸びにくい傾向があります。また、例え模範解答の要素を書いていなかったとしても、一貫性や妥当性があれば加点してもらえます。
本試験問題においても真逆の結論で各予備校分かれることもありますが、LECの解説講義では「ウチはこう考えるけど、妥当性を明確に表現できてれば逆の結論になっていてもOK」とハッキリ発言されることも多いです。
ぶらんちはTACとLEC両方の公開模試を受けて、以下のように用途(目的)を使い分けていました。
- TAC公開模試
受験生の中での現在位置の確認 - LEC公開模試
自分の解答プロセスの定着具合の確認
まとめ
如何でしたでしょうか。
ふぞろいな合格答案は「どのような回答を書けば合格レベルか」の指針にはなるけれど、あまり固執しすぎず解答作成プロセスを大事にしましょう、というお話でした。
ただ、ふぞろいな合格答案が成長の道しるべになるのもまた事実。上手に活用して2次試験合格をつかみ取りましょう!