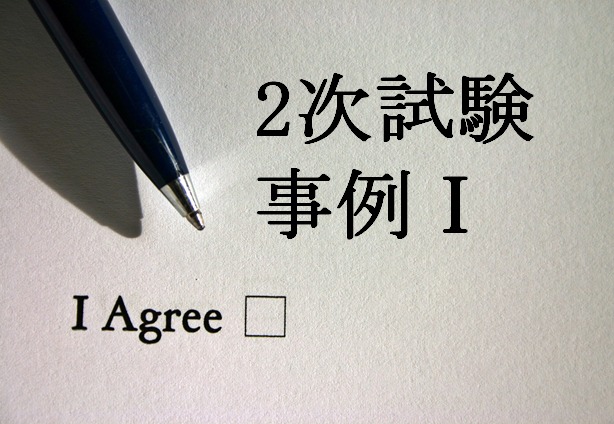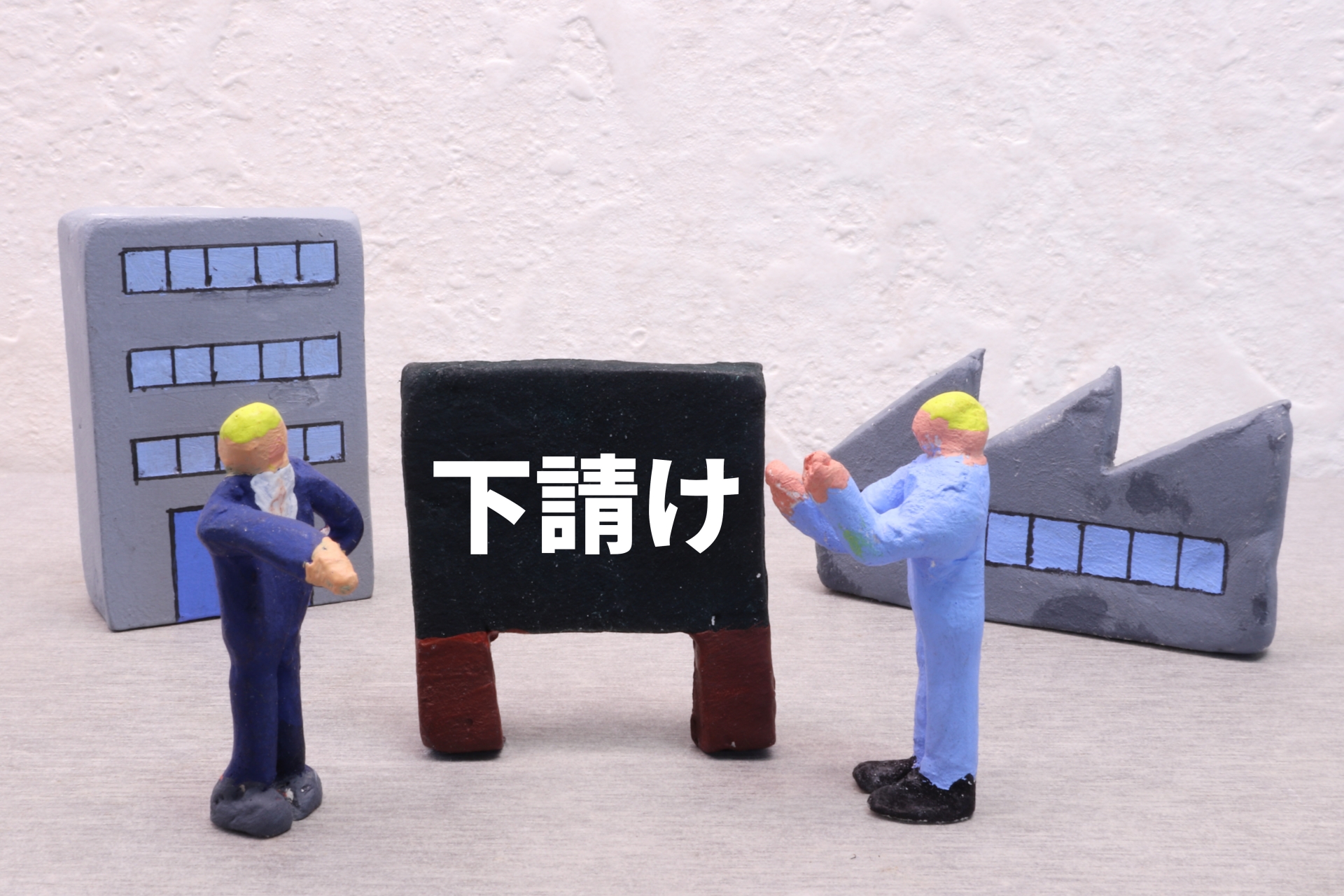ふぞろいで採点してみた(R3年事例Ⅱ)
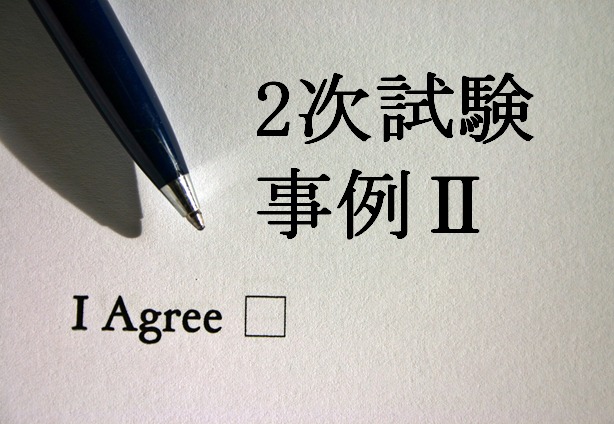
こんにちは。ぶらんちです。今回は事例Ⅱです。
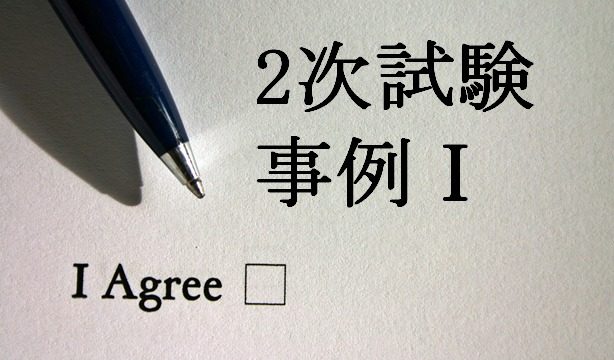
令和3年度事例Ⅱについて
令和2年度の事例Ⅱの事例企業は、豆腐の製造販売業者です。問題文は以下より入手できます。
また、令和3年度のふぞろいはコチラです↓
ぶらんちの回答案
詳細は以下にて解説しています。
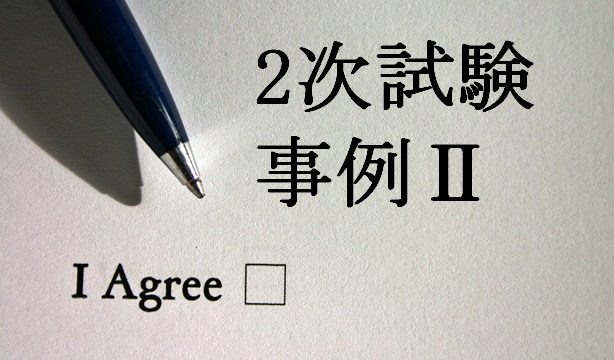
第1問
令和3年度事例Ⅱ 第1問(配点 20 点)
2021 年(令和 3 年)8 月末時点の B 社の状況を、移動販売の拡大およびネット販売の立ち上げを目的として SWOT 分析によって整理せよ。①~④の解答欄に、それぞれ 30 字以内で述べること。
- 強み(S)
①地元産大豆3、水にこだわった2豆腐の品質、②Y社との良好な関係。 - 弱み(W)
①受注用サイトのノウハウがなく3、②主婦層の顧客が少ないこと2。 - 機会(O)
自宅での食事にこだわりを持つ家庭が増えていること3。 - 脅威(T)
人的接触が避けられ1オフラインでの集客が難しい2こと。
⇒ 16点/20点(ふぞろい採点基準)
令和に入ってから3年連続でのSWOT分析でした。ふぞろいの評価も「みんなができた」となっているとおり、あまりここでは差はつかなかったと思います。
第2問
令和3年度事例Ⅱ 第2問(配点 25 点)
B 社社長は社会全体のオンライン化の流れを踏まえ、ネット販売を通じ、地元産大豆の魅力を全国に伝えたいと考えている。そのためには、どの商品を、どのように販売すべきか。ターゲットを明確にした上で、中小企業診断士の立場から 100 字以内で助言せよ。
全国の食通4をターゲットに手作り豆腐セット4をY社1サイトで販売3する。コラボ企画1と称し豆腐丼3のレシピを添え1Y社の米とペットボトル入り水をセット販売2し、地元産大豆の魅力を訴求3しつつ他ECサイトとの差別化を図る。
⇒ 22点/25点(ふぞろい採点基準)
ここはじっくりと与件文が分析できていれば取れた設問かと思います。問題は本試験の緊張感で冷静にパズルを組み立てられるかです。時間内で整理するためには、ひらめきも必要だったりします。
ちなみに実務でも、色々な情報を組み合わせて新サービスを提案することはあります。ですが、さすがに「80分で答え出せ!」なんてことは言われないし、ネットや本で調べることも誰かに相談することも可能です。なので事例Ⅱで「ひらめかない」方も、ちゃんと診断士活動は出来ますので、安心してください(笑)。
第3問
令和3年度事例Ⅱ 第3問(配点 30 点)
B 社のフランチャイズ方式の移動販売において、置き配を導入する場合に、それを利用する高齢者顧客に対して、どのような取り組みを実施すべきか。中小企業診断士の立場から⒜フランチャイザー、⒝フランチャイジーに対して、それぞれ 50 字以内で助言せよ。
- フランチャイザー
冷蔵ボックス1での鮮度の確保方法を確立5して周知徹底する。チラシ2を作成・配布6して利用者拡大を図る1。 - フランチャイジー
顧客とのやり取りは電話3にて行い、要望の収集5や季節商品の情報提供5を行う。密に連絡を取り愛顧を高める2。
⇒ 30点/30点(ふぞろい採点基準)
こちらも与件文にあるフランチャイザー・フランチャイジーの役割分担からパズルを組み立ててれば、そこまで書くことには困らなかった(と思います)。
まあ、30点満点はさすがにまぐれだと思いますので、あまり気にしないでください。
第4問
令和3年度事例Ⅱ 第4問(配点 25 点)
B 社では X 市周辺の主婦層の顧客獲得をめざし、豆腐やおからを材料とする菓子類の新規開発、移動販売を検討している。製品戦略とコミュニケーション戦略について、中小企業診断士の立場から 100 字以内で助言せよ。
製品戦略は同地の和菓子店6と新素材の菓子として共同開発する。柚子や銀杏と組み合わせ月替わり商品3も販売する。コミュニケーション戦略は、和菓子店では試食を行い2、移動販売ではIMによる5商品紹介で魅力を訴求する。
⇒ 16点/25点(ふぞろい採点基準)
ここもセオリー通りに解いていけば、和菓子店との協業は想起出来たと思います。逆に全く思いつかなかった方は、少し過去問の分析が足りない可能性があります。過去5年分で良いので、しっかりと過去問分析をする時間を作りましょう!
まとめ
如何でしたでしょうか。
ふぞろい採点結果は、84点でした!
本番でこの点数が帰ってきたら泣いて喜びますね。
次回は事例Ⅲです。お楽しみに!