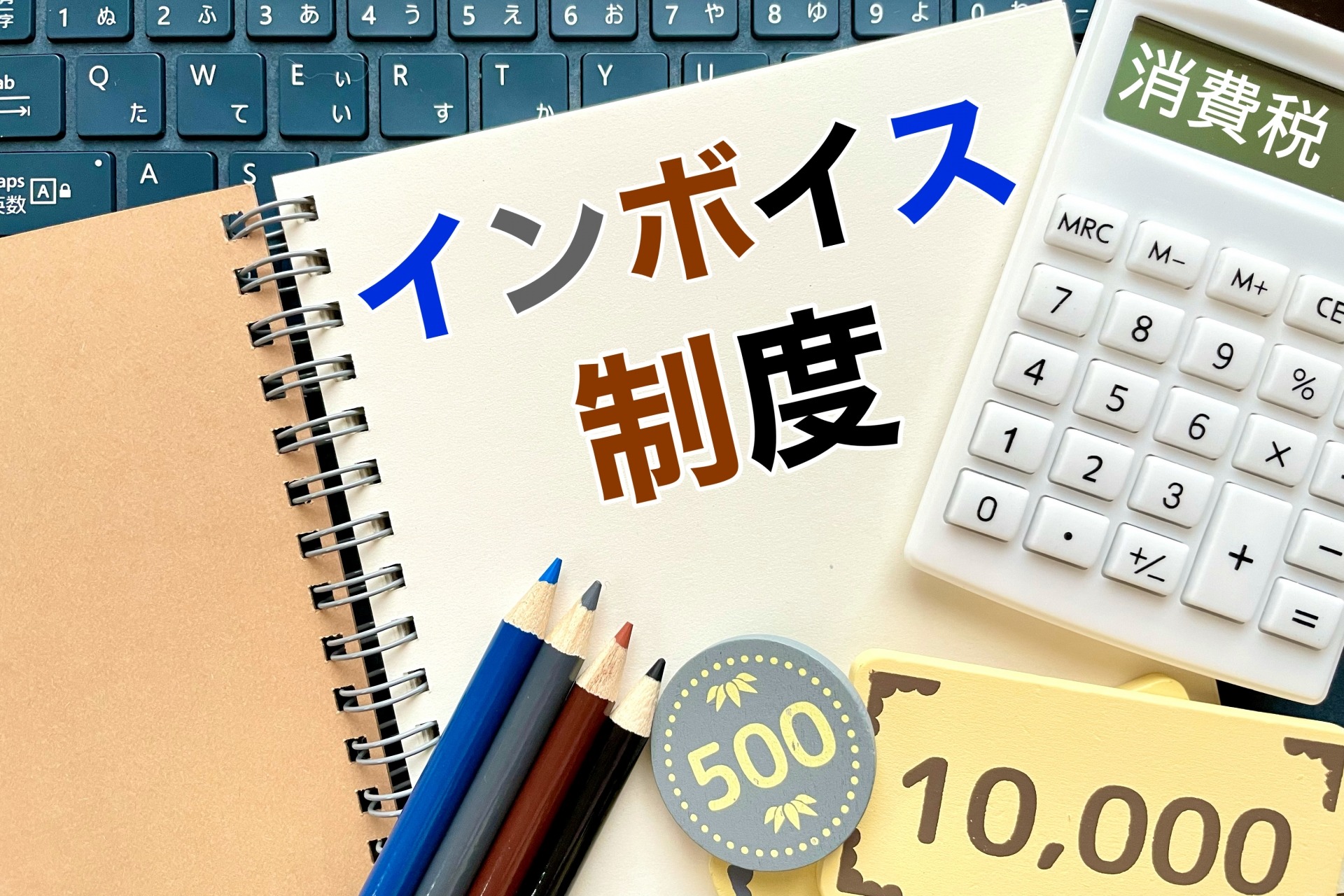用語の定義を正しく押さえよう①
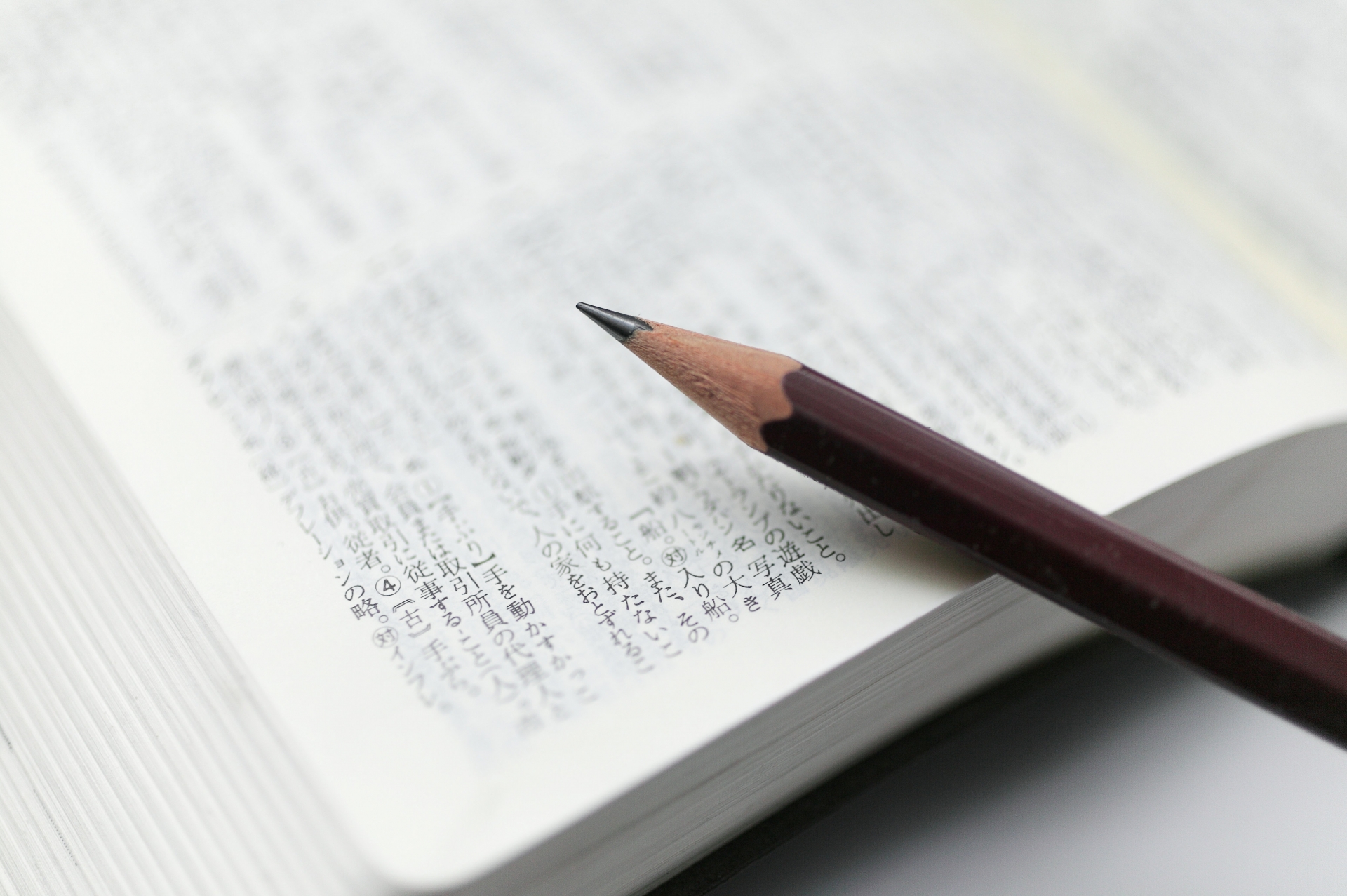
こんにちは。ぶらんちです。中小企業診断士試験では、用語の定義を正しく理解していないと回答できない設問も多いですよね。今回は、ぶらんちが引っかかった用語の定義をピックアップして紹介します。
周知性・著名性
経営法務、特に不正競争防止法で重要な定義です。
- 周知性
需要者の間に広く認識されている状態 - 著名性
全国で知れ渡っている状態
周知性はその市場で広く認識されている、具体的には隣接県など一地方で知られている状態のことを言います。一方、著名性は全国的な知名度がある状態を言います。
不正競争防止法にある周知表示混同惹起行為は、周知性のある商品・サービスと同一・類似の表示を使用することで混同を表示させる行為のことです。同じ営業地域において紛らわしい表示で気を惹くのはダメ!ってことですね。
一方、著名表示冒用行為は、著名性のある商品・サービスと同一・類似の表示を使用する行為のことです。全国的に知られているものは一般的に高い品質、ブランド力を持っているので、混同というよりもフリーライド(ただ乗り)や価値の希釈(ダイリューション)、汚染(ポリューション)を防ごうというのが主旨です。
知名度により主旨が微妙に異なっているので要注意です。

補助金・助成金・融資
中小企業政策で重要となる定義です。中小企業診断士に合格した後の方が大事になってくるかもしれません。
- 補助金
申請に対し内容審査があり、採択されれば給付される - 助成金
要件を満たしていれば必ず給付される - 融資
事業用資金の借入れ
補助金と助成金は返済の必要がありません。補助金は要件を満たした上で内容審査があり、採択された場合に限り給付されますが、助成金は要件を満たしていれば必ず給付されます。
一方、融資は借入れのため返済の必要があります。中小企業は大手企業に比べ財務体質がぜい弱であり、革新的な商品やサービスのアイデアがあっても資金を集められず(金融機関から融資を受けられず)、実現できないことも多いです。国・自治体の融資制度は、そんな中小企業を支援するために低利子・無利子でお金を貸してくれる制度というわけです。

1次試験の勉強方法(中小企業経営・政策)
事業再構築補助金
補助金の代表例でいえば、最近では事業再構築補助金だと思います。
事業再構築補助金はコロナ禍で売上が減少している事業者が、新分野展開や事業転換をするための支援を行う制度です。給付を受けるためには事業計画書等を作成し、新規性や実現可能性について審査を受ける必要があります。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために支給されるものです。
もともとあった制度ですが、コロナ禍の影響により注目を集めています。
課題・問題点
こちらは何度かご紹介していますね。詳細は下記記事参照。

1点だけ、事例Ⅳの経営分析で課題を訊かれることがありますが、これだけは問題点と捉えてよいとされています。
令和2年度事例Ⅳ 第1問
(設問1)
D 社および同業他社の財務諸表を用いて経営分析を行い、同業他社と比較した場合において、D 社が優れていると判断できる財務指標を1つ、課題となる財務指標を2つあげ、 a欄に名称、 b欄に算定した数値を、それぞれ記入せよ。なお、 優れている指標については①の欄に、課題となる指標については②、③の欄に、それぞれ記入すること。また、数値については、 b欄のカッコ内に単位を明記し、小数点第3位を四捨五入すること。
(設問2)
D 社の財政状態および経営成績について、同業他社と比較した場合の特徴を 60 字以内で述べよ。
この流れだと、設問2にどんな課題なのかを回答してしまいそうですが、あくまで経営分析の3指標(収益性、効率性、安全性)が良いのか悪いのかを回答するのがセオリーです。
まとめ
如何でしたでしょうか?
もっと紛らわしい用語の定義がたくさんあったはずなんですけど、全く思い出せません…(あんなに勉強したのに…)。思い出したら追加していこうと思います。
覚えていると思っている用語も、もう一度定義を確認してみましょう!