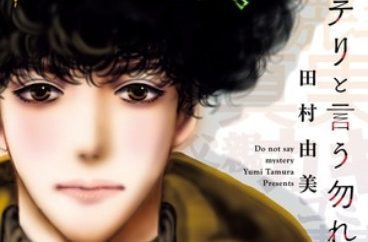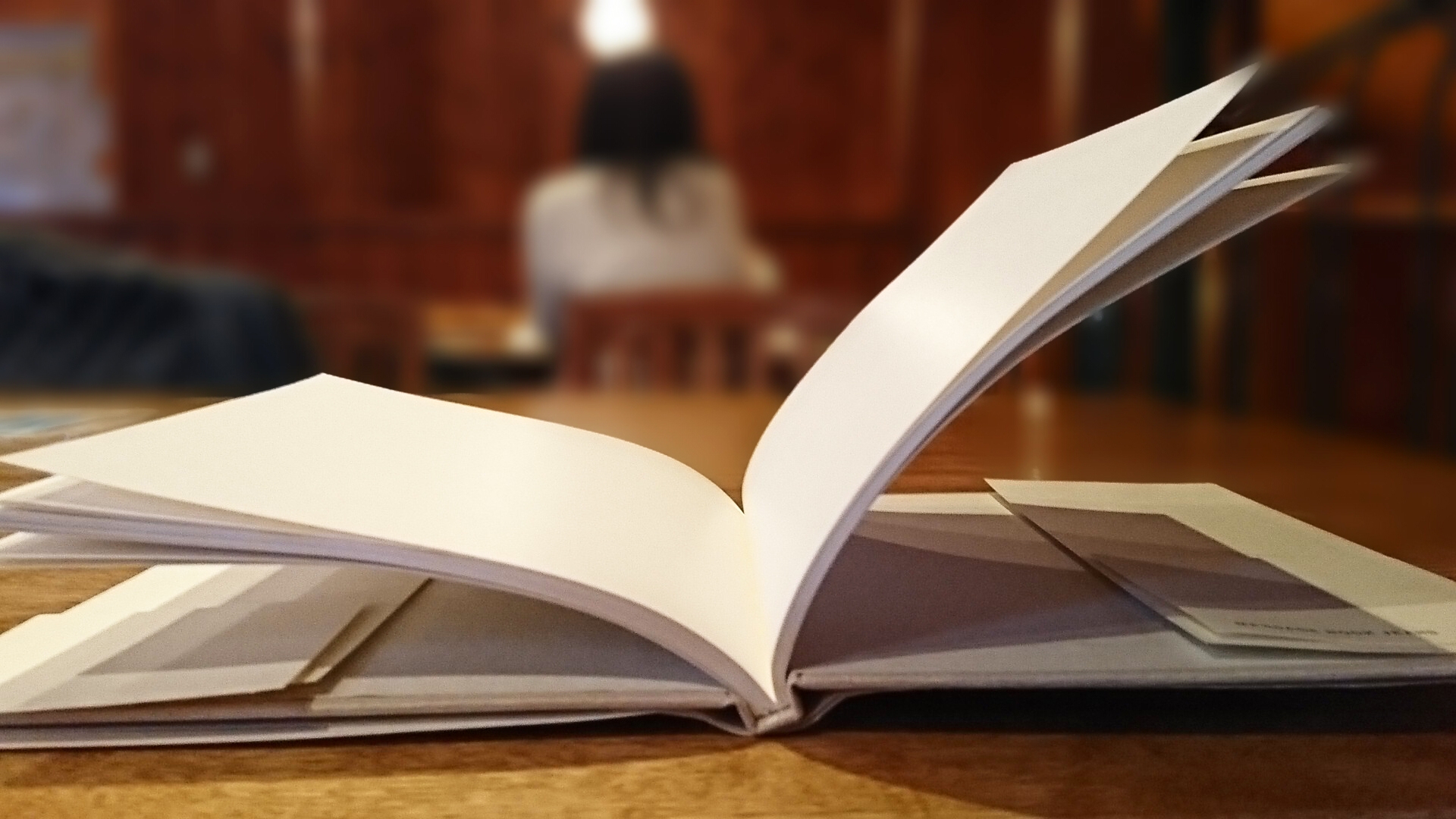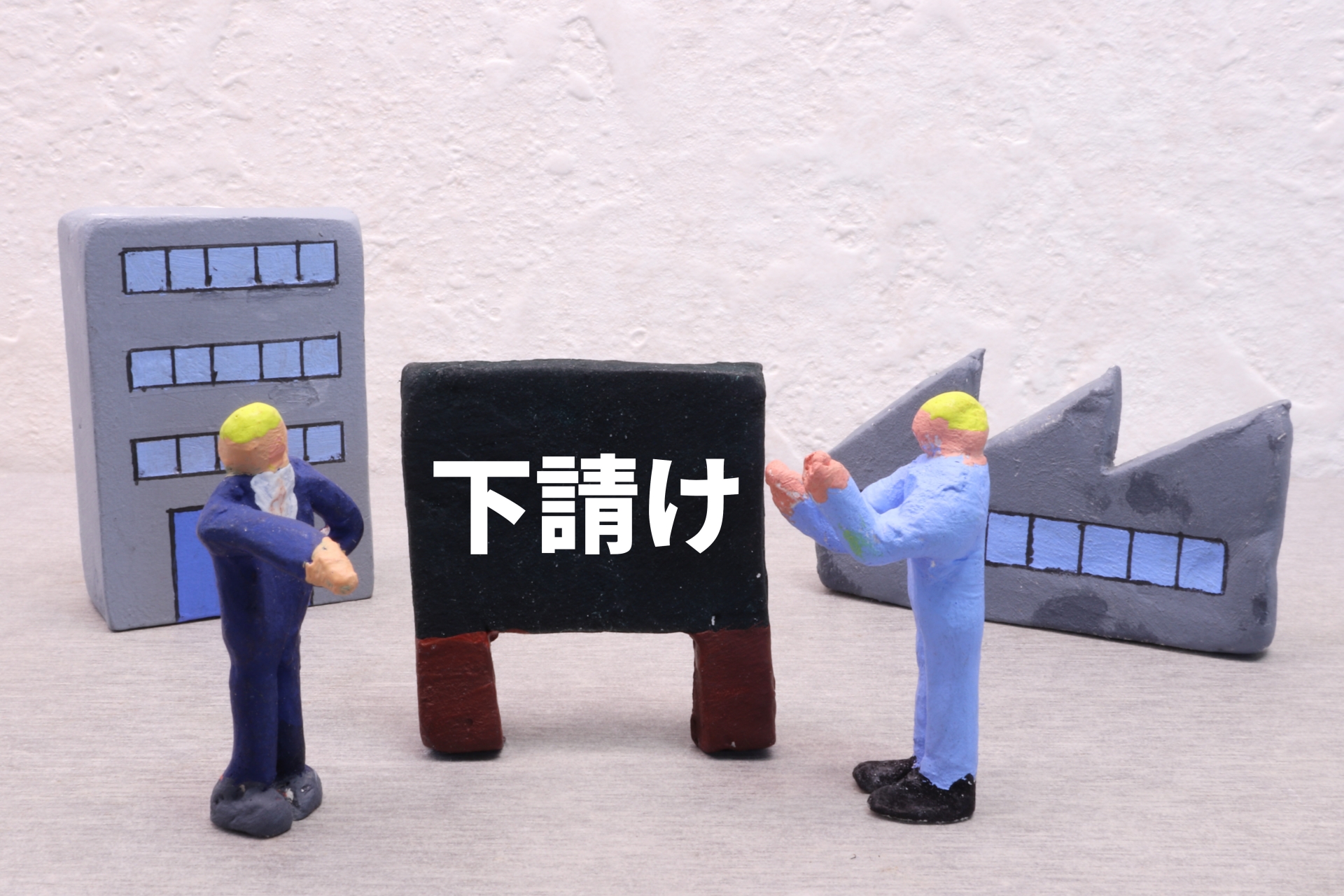「プラトー効果」とは?停滞期を抜け出す対処法について

こんにちは。ぶらんちです。
プラトー効果(別名:高原現象)とは、一時的な停滞状態のことです。仕事や勉強・スポーツ等、どんな分野においても、おおまかには学習量・練習量に比例して上達していくわけですが、直線的なグラフではありません。
上達と停滞を繰り返しながら、少しずつ成長していきます。ただ、停滞期にモチベーションを保つことは大変です。学習量・練習量が低下・あるいは辞めてしまっては、それ以上成長できなくなってしまいます。
今回は、プラトー効果の概要と対処方法についてご紹介します。
プラトー効果とは
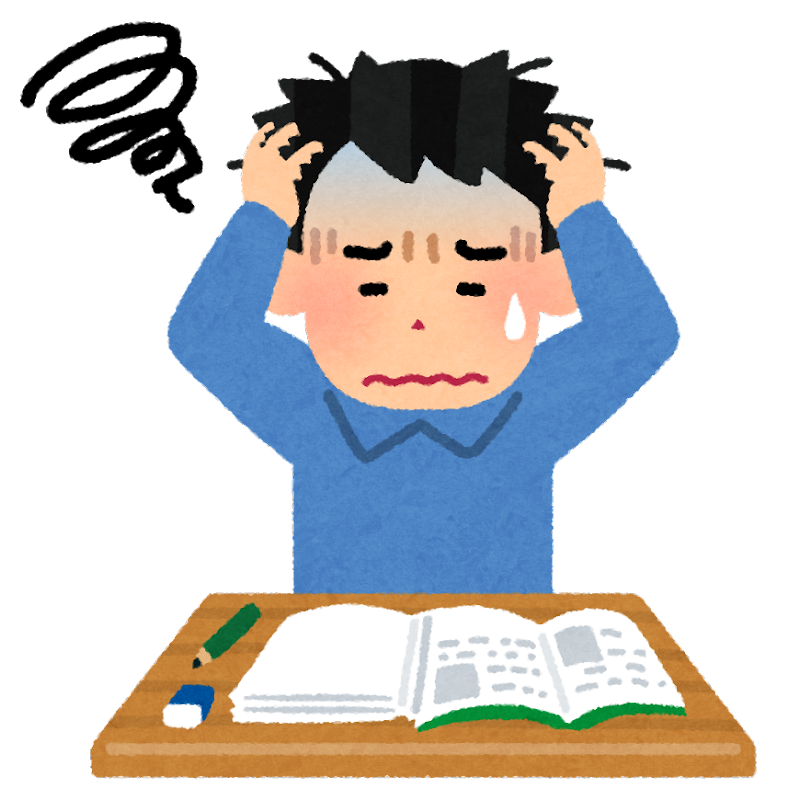
プラトー効果とは、何かしらの努力を続けているにも関わらず、成長を感じられなくなってしまう状態をいいます。
中小企業診断士試験においても、始めた頃は学習時間に比例して点数が伸びて、成長を感じられたと思います。新しい知識を得るのが楽しくて、積極的に勉強を進められた、という方も多いと思います。
ところがある時から、どんなに努力しても点数が伸びず成長を感じられなくなってしまう時期がやってきます。これがプラトー(高原状態)です。長い期間挑戦し続けている受験生の方は経験があると思いますが、プラトーに陥ると、結果が出ないことに落ち込み、あるいは不貞腐れて、学習意欲が著しく低下してしまいます。
プラトー効果に陥る原因
技術というものは、上のレベルに行けば行くほど、たくさんの知識を使って、複雑な動作や処理を速く正確に行うことが求められます。最初の頃は覚えたことを単純にアウトプットするだけだったのに、上のレベルに行くにつれて「使いこなす」ことが重要になってきます。
※「使いこなす」の重要性は以下記事でも書いています。
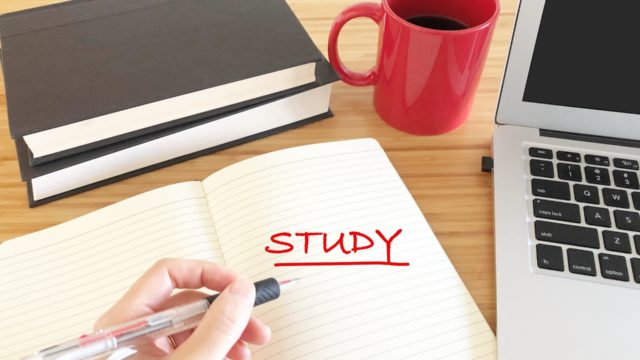
なので当然、次のレベルに進むまでに必要な学習量・練習量は多くなっていき、次第に成長を感じられない時期が長くなる(停滞期)というわけです。
また、プラトーに陥る原因として心的飽和(慣れ)や疲労も挙げられます。
心的飽和(慣れ)とは、最初は新しい知識に刺激を感じ新鮮な気持ちで学習できていたものが、いつしか「当たり前」となり、そこから得られるものは無いと感じてしまう状態といいます。いわゆるマンネリ化です。
疲労についてはまあ当然ですよね。学習量は「学習時間×集中力」で表されます。疲れが溜まっていては集中力が続かず、いくら長い時間勉強しても、学習量は伸びなくなってしまいます。
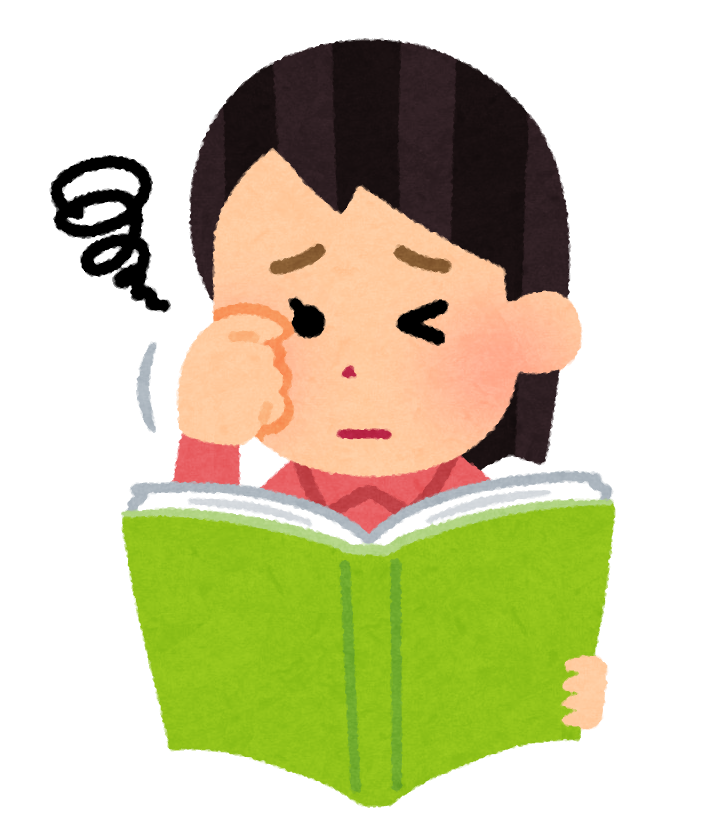
プラトーに陥った時の対処法
ご紹介する対処法は3つです。
- プラトーの状態にあることを認識する
- 学習方法を変えてみる
- 少し休む
プラトーの状態にあることを認識する
プラトーに陥ると、「自分は能力が低い」「自分の才能ではここまで」と、とかくネガティブになりがちです。ただ、ネガティブ思考なんて百害あって一利なしです。
「自分はプラトーの状態である」ことを認識することで、「ここを抜ければまた成長できる」とポジティブに捉えるよう心がけましょう。「プラトーは誰しも必ず訪れるもの」と割り切る気持ちが大切です。
学習方法を変えてみる
いつも決まった時間帯・場所で勉強をしていると、マンネリ化が進みプラトーに陥りやすいと言われています。計画的に試験勉強を進めるために学習環境を整備することは大事なことですが、あまりにルーティン化すると脳への刺激が無くなってしまうということですね。
そこで、勉強する時間帯や場所を変えてみたり、1日に複数の科目を勉強してみたり、1次試験と2次試験の勉強を並行で進めてみたりと変化をつけてみましょう。
ちなみに、筋力トレーニングの世界では「自分の限界を少し超えるくらいの負荷をかけないと、筋力はアップしない」というオーバーロードの原則(過負荷の原則)というものがあるそうです。
試験勉強でも同じで、「出来ることを繰り返していてもパフォーマンスは上がらない」「パフォーマンスを上げたければ当たり前の基準を高める」という意識が大事です!
少し休む
学習量は「学習時間×集中力」と書きましたが、疲労回復には休息が一番です。「休んでいる間にもライバルたちが勉強している…!」と気が休まらない方は、だいぶお疲れじゃないかと思います。
2次試験はともかく、1次試験は絶対評価です。7科目合計で420点を取れば全員合格なわけで、420点以上を目指すこともライバルを意識することも、実際は何の意味もないです。
中小企業診断士試験は、勉強時間が1,000時間とも言われる試験です。長丁場ですので、少し肩の力を抜いても構わないと思いますよ!

まとめ
如何でしたでしょうか?
ちなみに脳の「上達と停滞」の仕組みを逆手にとって、短い時間で大量の知識を記憶する勉強法があるそうです。
興味がある方は一度手に取ってみては如何でしょうか?