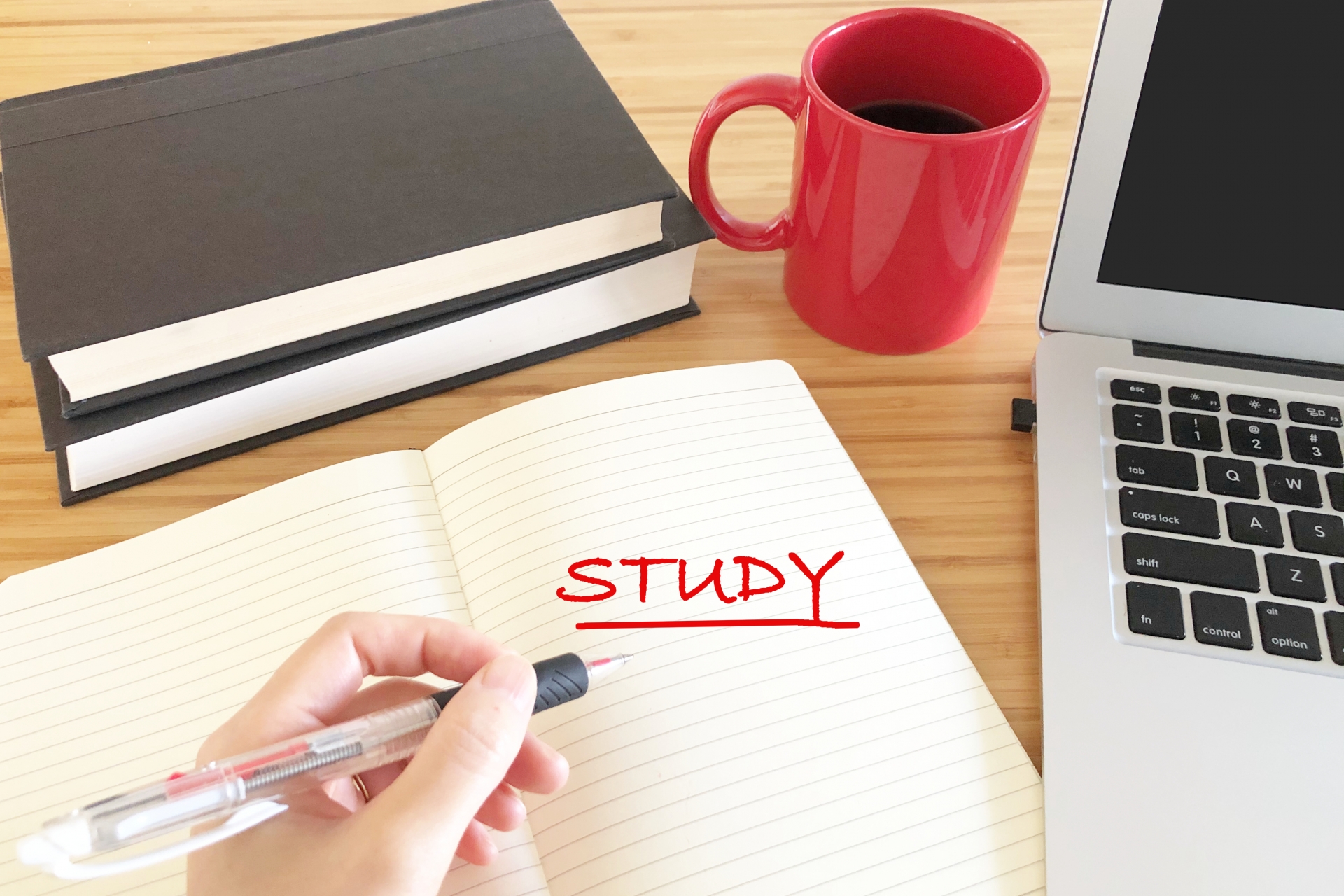診断士資格をどう活かす?あなた自身の事業計画書をつくろう!
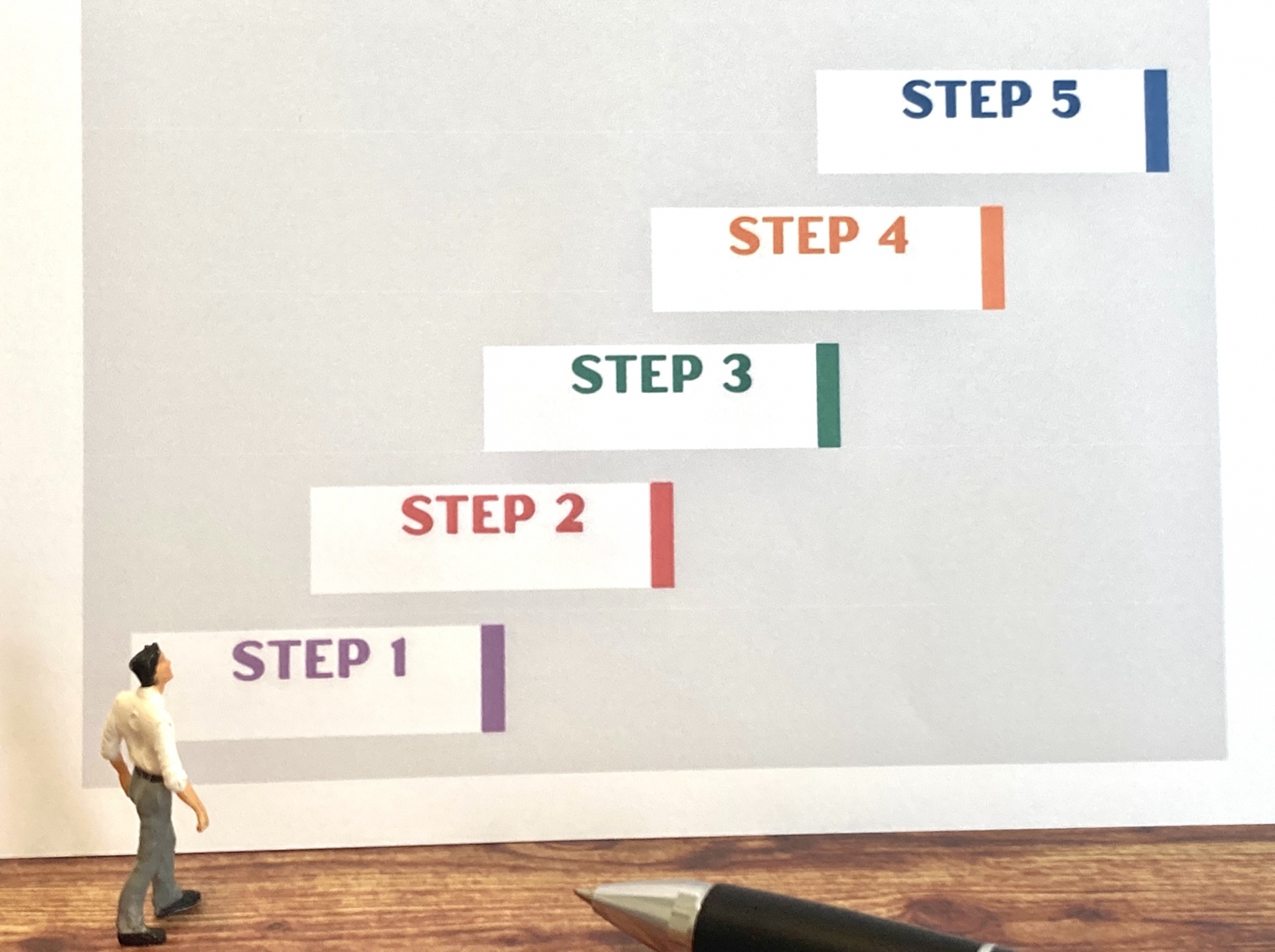
こんにちは。ぶらんちです。本ブログは「中小企業診断士を目指す受験生」向けに様々な記事を投稿していますが、「中小企業診断士になれた後は、実際どうやって活かすのか?」も気になるところだと思います。
本日はそんな「中小企業診断士の実態」から、「将来像を考えよう」がテーマです。
診断士に合格しても活かせない人が多い
先日「タイプ別 中小企業診断士のリアル」という書籍を読みました。本書によると、中小企業診断士は大きく分けて5つのパターンに分かれるとのことです。
- 資格取得が最終ゴール型
- 企業内診断士・自己啓発型
- 企業内診断士・副業型
- プロコン・C型(コネで仕事を受注し、中小・零細企業にサービスを提供)
- プロコン・D型(直接仕事を受注し、中堅・大企業にサービスを提供)
各タイプの特徴や詳しい活動実態は本書を読んで確かめて頂きたいのですが、実は「資格取得が最終ゴール型」が一番多く、資格を活かさずに終わらせてしまう人が多いということが如実に書かれています。
これは私自身すごく感じることでした。例えば、大学に合格すると入学説明会やテキスト購入などの準備期間の後、明確に決められた日からキャンパスライフが始まりますよね。就職にしても、社員研修があったり業務説明があったり、ある日からその会社の一員としての生活が始まります。
でも診断士って、合格のあと明確なスタートがないんです。「3年の間に実務ポイントを集めよ」という裏ハンター試験みたいな通過儀礼はありますが、診断士バッチは協会に入らないともらえないし(でも入会は任意)、セミナーやフォーラム、説明会、研究会、勉強会なんかも強制参加のものは1つもありません。
言い換えると、能動的に動く人にはどんどん情報もチャンスも回ってきますが、受け身の人には何の変化も起こらないです。イベント等を全てスルーすれば、元の生活と何も変わらないわけです。「診断士資格を取れば、そこから人生が変わる!」と思っていたのに、「結局何も変わらなかった」と勝手に失望して辞めてしまう、という悲劇が後を絶たないわけです。
ちなみに、プロコン・D型として活躍するためには高いハードルをいくつも乗り越える必要があり、プロコン・C型とは求められるスキルも違うので徐々にステップアップして辿り着けるものでもない、ということも書かれています。
要は、合格後は情報収集を行って、「自分はどこを目指したいか」を考え、それに向かって計画を立てることが必要ということです。
自分についての事業計画書をつくろう
2次試験の大まかな解法は「設問文から回答のあたりをつける→与件文からSWOT分析→強みを活かす・弱みは克服する方法を助言」です。そしてキーワードは「選択と集中」です。
実際の経営診断も「業界動向を予めチェックして課題のあたりをつける→社長のヒアリングからSWOT分析→強みを活かす・弱みは克服する方法を助言」といった流れなので、合格者は試験勉強を通じて経営診断の基礎を身につけていると考えてよいでしょう。
といっても、コンサルティング経験がないのにいきなり現役社長に助言するのは勇気が要ります。「誰かやり方を教えてくれよ!」と言いたいところですが、中小企業診断士は独占業務がない代わりに色々な活躍の仕方があって千差万別です。なので「自分が思う正解」は教えられても、「あなたにとっての正解」は誰も教えてあげれないです。
そこで、まずは自分自身をクライアントに見立てて、強みを活かす事業計画書を作ってみましょう。自分がどんな道に進みたくて、そのためには何をすれば良いか明確化することで、診断士資格を活かす方法が見えてくると思います。
以下は事業計画書を作るに当たっての情報整理の仕方です。あくまで一例なので、自分がまとめやすい順番で整理するとよいかと思います。
SWOT分析をする
最初は現状分析です。自分の強みと弱み、機会と脅威を洗い出します。
例えば、「中小企業診断士」業界について情報収集したとします。中小企業診断士は経済産業省の管轄なので、同省が打ち出す政策、特に中小企業向けの施策は中小企業診断士にも求められる役割があり、それらはすなわち「機会」と言えます。
経済産業省の政策や思惑は、中小企業白書や小規模企業白書からも読み取ることができます。中小企業の動向に合わせて補助金や制度づくりをするわけなので、当たり前といえば当たり前ですね。

機会に対して出来ることが「強み」であり、対応できないものが「弱み」です。最初は「強みと言えるものがない」と思うかもしれませんが、会社勤めで得た何気ないスキルやノウハウも「それらの知見を持った診断士」が少ない場合は十分強みになります。
弱みと脅威の分析は後回しで良いです。経営リソースが少ない企業の基本戦略は「選択と集中」でしたよね。「自分」においても、弱みの克服よりも強みの強化にリソースを割くべきです。

ありたい姿を設定する
企業でいうところの「経営理念」「経営ビジョン」です。誰に見せるわけでもないので、「中小企業を支え社会貢献したい」なんて大層なものでなくても、最初は「生活に余裕を持ちたい」「いい車に乗りたい」みたいな下世話な感じでぜんぜん良いと思います。
ちなみにぶらんちは「会社に縛られない人生にする」でした。「やってて楽しい」「やりがいがある」と感じる仕事だけで食べていける状態、が最終目標です。
課題を洗い出す
理想と現実のギャップが課題でしたよね。ありたい姿(理想)を設定したら、そこに辿り着くためのギャップを整理します。
収入面
現在の年収はすぐ分かると思うのですが、「このままだと生涯収入はどのくらいになるか」も計算します。上司や先輩を眺めつつ、何も変わらずに歳を重ねた場合にどのような将来が待っているかを想像します。
その上で、ありたい姿を実現するにはどのくらい収入アップが必要かを計算します。ありたい姿が「年収XXXX万円!」なら現在の年収とのギャップで分かりやすいです。そうでなくても、ありたい姿に挑戦するための軍資金だったり、何かの資格を取るための費用だったり、独立してから収入が安定するまでの生活資金だったり、収入に絡むことは色々あると思いますので、それらを整理します。
スキル面
ありたい姿を実現するために必要なスキルを洗い出します。もし「ITに強い中小企業診断士」で独立したい場合でも、DXなのかAIなのか、どの分野で活躍したいかによって必要な技術って違いますよね。もっというと、そもそも開業ってどうやるのかとか、青色申告と白色申告の違いとか、診断士試験には出てこないけど必要な知識って結構あるんですよね。
解決策を考える
課題の洗い出しが出来たら、解決方法を考えます。それらが事業計画の中身になっていきます。
強み×機会でアイディアを出す
ありたい姿になるためのビジネスモデルを考えます。文章能力を活かした執筆活動とか、プレゼン能力を活かしたセミナー講師とか、IT専門のコンサルティングとか、まずは「強み×機会」で差別化が図れそうなアイディアを出します。
その上、それらを実行するためのプロセスや収入について調べます。そうすると執筆活動は単価が安くて膨大にこなす必要があるとか、コンサルティング契約に辿り着くには公的機関の専門家登録するのが意外と近道とか、具体的な情報を見つけられるようになります。
それらを組み合わせ、もしくはアイディアを見直して「ありたい姿に到達できそうなビジネスモデル」を作成します。
合格同期や先輩診断士の話を参考にする
インターネットでは一般的な情報は出てくるものの、「具体的な情報」はなかなか出てこないです。なので合格同期や色々な先輩診断士のご経験をお伺いするのが一番早いです。
まずは協会に入会してイベント情報を入手できる環境にする→イベントや研究会・勉強会に積極的に参加して他診断士との交流を持つ、というのがかなり有効です。いろんな話を聞くことで、より良いアイディアも生まれるかもしれません。
弱みの克服は…?
「弱みの克服よりも強みの強化にリソースを割くべき」と書きましたが、克服しないとマズい弱みもあります。例えば、独立したい場合の「開業の仕方」「仕訳」「確定申告」などです。ただ、そういうものは外部リソースを活用すればたいてい解決します。
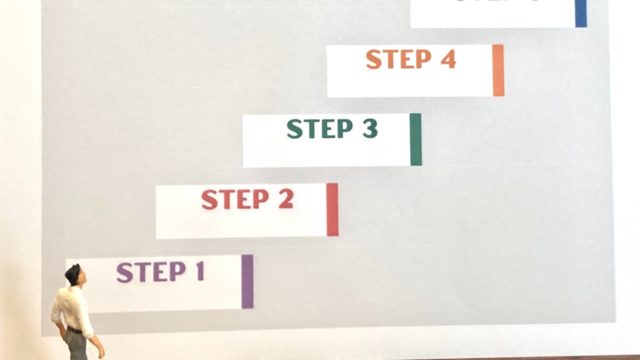
上記は極端な例ですが、弱みは「人にやってもらう」方向で考えて、このコスト分の売上をどう捻出するかを考えた方がスムーズです。
実行計画を策定する
解決策が整理出来たら、具体的なスケジュール(WBS)に落とし込みましょう。コストが発生する場合は、資金調達計画も策定します。
「アイディアが固まらない」など、そもそも解決策が整理出来ないといった場合は、「いつ何のイベント(講習会や説明会等)に参加する」等、解決策の整理に至るアクションもスケジュールに加えてしまいましょう。
とにかく、次のアクションに日付を設定し、「考えたけどやらなかった」「忙しくてできなかった」とならないようにすることが肝心です。
予実管理する
つくった事業計画書を実行に移します。予定と実績を照らし合わせて、遅れている部分のリカバリーや計画の見直し等、PDCAサイクルを回します(予実管理)。
ここまで出来れば、まず間違いなく現状よりも絶対に良い未来が訪れます。コンサルティングスキルも磨かれますし、自信もつきますよ!
まとめ
如何でしたでしょうか?
最初はラフなものでいいと思います。環境が変われば考え方が変わることも多いです。その都度ブラッシュアップしていけばいいのです。
とにかく「どうしたいか」「どうありたいか」を常に考える癖をつけておかないと、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性が高いです。仮に(考えたくないですが)診断士試験が不合格だったとしても、「自分自身の事業計画書」をまとめておいて全く損はないです。合格発表までのこの空いた時間を有効活用して、ぜひとも作ってみてください!