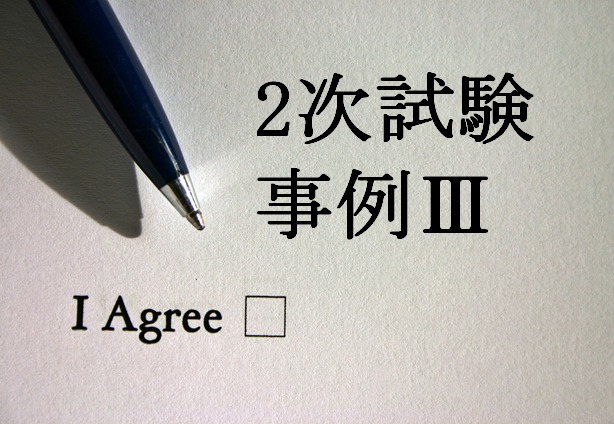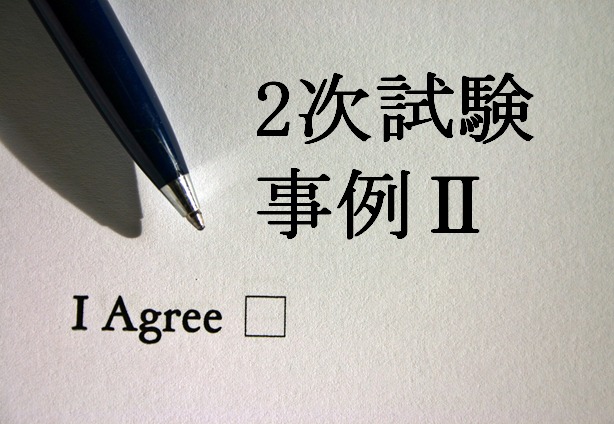すぐに2次対策をはじめよう

こんにちは。ぶらんちです。令和3年度1次試験の合格発表は9/21(火)ですが、あらかた合否の目途は立っているものと思います。今回はまだ2次試験問題を解いたことが無い方向けに、1次試験終了後から始める2次試験対策について紹介します。
残された時間は多いようで少ない
令和3年度2次試験は11/7(日)に実施されます。本記事の投稿日(8/27)から数えると残り72日しかありません。もし2次試験対策を全くしてこなかった場合、2か月ちょっとの間に多年度受験生にも打ち勝つチカラを身に着ける必要があります。
2次対策の標準的な勉強時間は200時間と言われています。今日から始めても、1日当たり3時間程度は勉強する必要があります。すぐに学習計画を立てて勉強時間を確保しましょう!

2次試験の概要をつかむ
2次試験の形式
2次試験は、1次試験のマークシート方式とは異なり論述形式で行われます。4科目に分かれており、全ての総得点が60%以上かつ40%未満の科目がない場合に合格となります。科目合格はなく、2回連続で不合格となると1次試験からやり直しになってしまいます。
| 日程 | 科目 | 試験時間 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 午前 | 事例Ⅰ(組織・人事) | 80分 | 100点 |
| 事例 Ⅱ(マーケティング・流通) | 80分 | 100点 | |
| 午後 | 事例 Ⅲ(生産・技術) | 80分 | 100点 |
| 事例 Ⅳ(財務・会計) | 80分 | 100点 |
2次試験は、ある事例企業の概要を説明する与件文と、それに対して診断と求める設問文に分かれています。与件文はだいたい2~3ページほどあり、事例企業の開業から現在までの変遷が書かれて、文中には問題点や課題が散りばめられています。設問文でそれらが問われ、改善策を論述回答する、といったイメージです。事例Ⅳについてはちょっと特殊で、計算問題がメインです。財務・会計の深い知識が必須となります。
上記の説明は、どの中小企業診断士関連のサイト・ブログにも書いてありますが、解いたことが無い人はイメージがつかめないと思います。ぶらんちも最初は「要は国語のテストでしょ?」と思っていました。実態は全く違うのですが、それを実感するために過去問を解く必要があります。
テキスト・問題集を入手する
まずは教材を揃えるところからです。2次試験の問題は中小企業診断士協会のHPから入手することはできますが、正解は公表されていません。試しに解いてみたところで良し悪しの基準が全く分からないので、教材なしで勉強を進めることが難しいです。
下記に定番の教材を紹介します。既に入手困難な可能性もありますので、見かけたら必ず購入するようにしてください!
その他(LEC模範解答集)
LECでは過去問題の模範解答を1年ずつ販売しています。
少し高いですがTACとは別の視点で分析しており、比較すると面白いと思います。
過去問を解いてみる
テキスト・問題集を入手したら、直近5年間のどの年度でも良いので過去問を一つ解いてみましょう。最初は「何を訊かれているか」「何を答えたらよいか」が全く分からないと思いますが、とにかく解答を書いてみます。
その後、模範解答と見比べてみます。解説を通じて与件文・設問文に散りばめられたヒントや、解答のレベル感などを確認してみましょう。そうして初めて「2次試験とはこんな試験」という概要がつかめるのです!
学習計画を立てる
過去問を解いて2次試験の概要をつかんだら、さっそく本試験までの学習計画を立てましょう。1事例解くのに80分、解説の読み込みや振り返りなどを含めると2時間はかかるので、ある程度まとまった時間が必要です。
1次試験のようにスキマ時間の積み重ねで時間を捻出することが難しいので、その点注意が必要です。
一方、事例Ⅳは計算問題が中心ですので練習量がモノを言います。経営分析やキャッシュフロー計算書作成、CVP分析や現在価値など、出題範囲は狭い代わりに複雑な処理を要求されますので、こちらも問題集を買ってひたすら問題を解いていきます。
以下に事例Ⅳ対策として有名な書籍(イケカコ)を紹介します。内容は正直本試験より難しいですが、頑張って解いているといつの間にか本試験が簡単に感じるようになる、厳しい修行のような本です。
市販でもう少し取り組みやすい問題集があると思うので、合わせてやるといいですね。
事例Ⅳの計算演習は毎日続けることが肝要です。30分でも良いので、必ず学習計画に盛り込むようにしましょう!
まとめ
如何でしたでしょうか?
2次試験の回答プロセスについては他記事で色々と書いていますが、以下はその入門編となっていますので、興味があれば合わせてご確認ください!